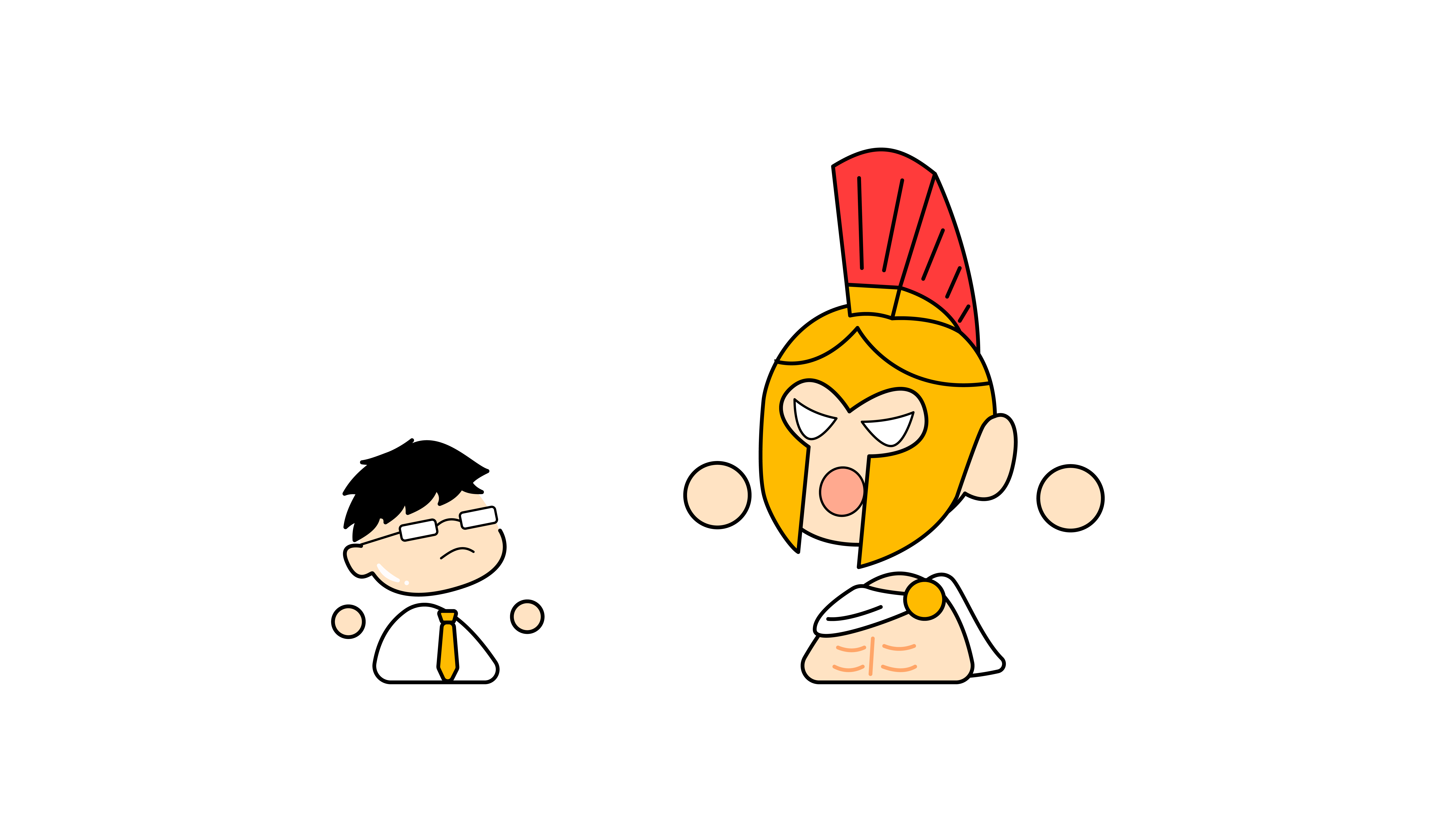
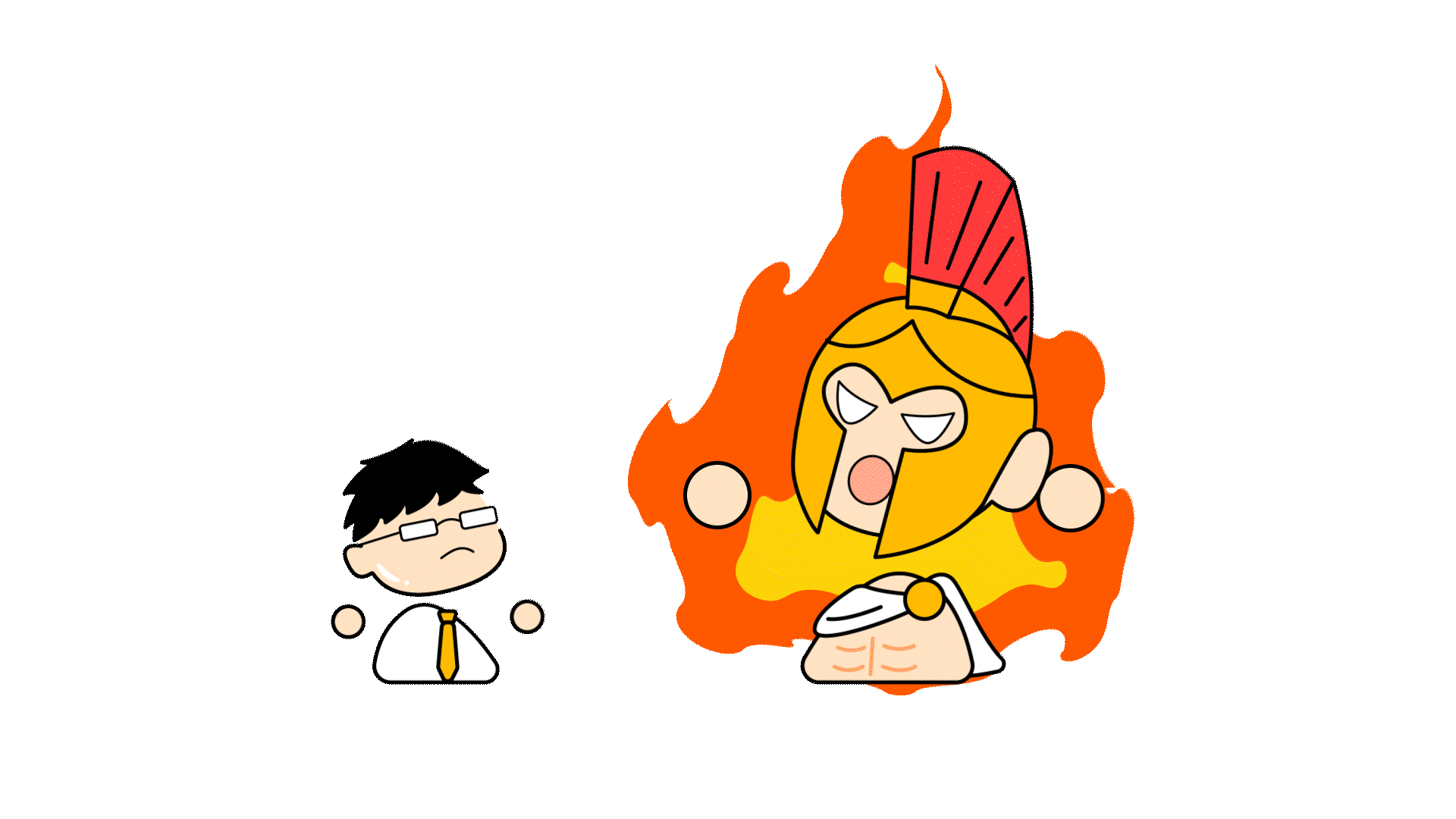
今回20代の転機というテーマで、私が小中学生時代に通っていた塾の恩師である秋山淳一先生(仮名)にインタビューさせていただきました。
秋山先生は関西塾の大阪校(仮名)で塾長をされています。関西塾は主に小中学生を対象とした、先生1人対生徒多数の集団個別型の教室です。先生はいつもどんな質問にも真剣に、熱く答えてくれ、大変お世話になりました。
私が大学進学で上京している都合で、ZOOMでのインタビューとなりましたが、お久しぶりに先生とお話でき、小中学校時代ではあまり伺ったことがなかった先生の人生のお話を聞かせていただきました。
プロローグ:先生の転機とは
20代の転機ということなんですが、先生にとっての転機はなにかありますか?
大学のアルバイトの20歳ぐらいからずっと塾で仕事をしてて、塾業界以外のことを知らないんですよね笑
ずっと今のA塾でですか?
今の関西塾はそのアルバイトとは別で、塾自体はいくつか行ってるね。最初バイトで行った塾は別の西日本塾やし、先生だけじゃなくて、教務って言ってな、教室運営の仕方を指導する立場で働いてた時もあんねん。
それで、塾で教える方が向いているなっていうので、先生の方向に
現場がやっぱり楽しいっていうのは、教務をやってみる前からあって、ただ、そういう目線に立って物事見てみたいなっていうのはあったわけ。現場は好きやけど、そういう立場に立ってみないとわからないことってあるやんか。そのために何年ぐらいかな、3、4年。そういう時期もあったな。そうね、転機って言われたら、なんやろ。劇的に変化したとかそういうのはないけど、ただ、そういう教務の部分も経験した結果、やっぱり現場で直接生徒に接しながら、教育関係に携わっていくのが自分には一番向いてるかなってのは確認できたな。
塾とともに生きる。
アルバイトから現在まで塾での仕事を続けている。
講師、教務と様々な視点で塾を見てきた先生。
塾との出会いこそが先生最大の転機なのだろうか。
第1章:塾への入口
最初の塾バイトを始めたのはなにかきっかけはありましたか?
それは、2つあって。まず1つは、先生って呼ばれてみたいなっていう笑。それと、自分で学んだ知識を伝えられたら役に立つんじゃないかっていうのがあったね。今まで勉強したことって使わへんやんか、塾の先生せんかったら。そう、だからそういう気持ちがあって始めたな。
就活ってしましたか?塾で働くにあたって
いや、してないよ。僕はもうそのまま(アルバイトで働いてたところに)残ったわけ。(就活が始まるころには)この業界で働くっていうのを決心してたから、就職活動はせずに。
その決心は塾に向いてたからっていうのがありましたか?
そうやな、ただのいち講師やったんやけど、その時の給料はよかった。ただの普通の講師や。一応、主任講師っていう肩書をもらってたんやけど、大学時代から。とりあえず1人でやっていくぶんには全然困らないぐらいの額やったなあ。大卒の初任給並みにはもらってたと思う。
塾との出会い。
これまで頑張ってきたことを活かせる仕事がしたいと始めたアルバイトだったそうだ。
何校くらい塾にいきましたか?
最初に(アルバイトで)行ったところに、一旦そのまま就職したからね。
最初のところですか。
そう、最初のところで、5年ぐらい、6年ぐらいかな。バイトの時期も含めたら6年ぐらい行って、変わったのよね。
その変わったところで教務の仕事をすることになるんですか?
そうそう、合ってる合ってる。主任講師としてしばらくやってたら、別の塾から教務の話がきて、教室の運営の仕方を指導する立場として働いてみませんかっていう話があったわけよ。
そうなんですね
教務ではどんなことをしてましたか?
塾の運営の仕事なんやけど。お金の話とか、教材はこれを使ってくださいとか、(先生達に)報告の仕方を教えたりする事務系の仕事とか。あとは、先生の派遣依頼の仕方とか。
はいはい。
本部で一括して先生を雇ってんねんけど、そのー、講師の希望する勤務先と教室との折り合いをつけたりとかもあったな。
教務は各教室にいるとかじゃなくて、ほんとに本部で仕事をするってかんじなんですね。
そうそう。その、直接運営にかかわる相談って言うんかな、生徒をどうしどうしたらいいですかとか、そういう感じではなくて、どちらかというと。こういう時どういう報告すればいいですかとか、先生が一人足りなくなったので補助してくださいとか。あとは、こんな教材あるんですけど使っていいですかとか、なんかそういう感じの相談が多かったね
ほぼ授業とは直接かかわらない感じですね。
でも、やっぱり個人的には生徒どうしたらいいですかっていう部分も気になるところやったから、個人的にはそういう相談も受けてたね。
どのくらいの期間でしたか?教務やってたの
2年かな。で、もう我慢できんくなって、現場に戻ったってかんじやな笑。新規開校する教室があるからっていう話があって、僕行きます!って。
生徒に教えるのと大人相手に教えるのとではまた違った大変さはありましたか?新しく勉強しないといけないこととか
大変さで言ったら授業してる方が、大変。でも、野心があったからね。将来は自分でやりたいって、思ってた。だから、結局そのための勉強。自分の中でなんで(教務の仕事)をやってみたいと思ったかって言ったら、将来的にそういう気持ちがあるからね。
1人で塾をやりたいという
そうそうそうそう。そのために必要、しておいた方がいいと思ったんで、そういう魂胆でやったって感じな笑。
そう。やっぱりね、人生って自分のやりたいことに自分を合わせていくんですよ。
はい。
自分に何ができるかじゃなくて、何をしたいからこれができるようになろうっていう考え方をやっぱりしていかなきゃダメですよね。
目標に向かって。
教務を経験することで自分のいるべき場所を改めて認識したそうだ。
第2章:きっかけとは
先生的に自分で塾を運営したりしたいなって思い始めた時期ってありますか?
そうやな。最初のバイトをし始めて、大学3,4年生ぐらいかな。ちょっととんでもない教室長が来てさ笑。であの人がきっかけかな。なんか簡単に言うと、もう生徒のためならなんでもするでしょみたいな、全然やるでしょみたいな、そういう感じの人で。残業も普通に強いるし。大学生に笑。で、授業の準備に最低30分以上早く来なきゃダメだとか。
結構スパルタタイプな笑
そうそう笑。あと、懇談とか保護者相談も、あの当時は教室長がやってたんやけど、できるだけ講師も行きなさいみたいな。当然のようにいろんな縛りをつけていった。そういう教室長が来て、今でこそ、なんていうか必要やったって思うところはあるんやけど、伝え方よね。で、何人も先生が(その教室長が来てから)辞めていった。僕もいろいろ振り回されて、やっぱりこう、組織で働く時ってどうしても上司がいて部下がいる。そういうやっぱり少なからずこの縦の関係がやっぱりあるのかなって思ったときに、上司に恵まれなかったら、自分の能力生かされへんなと。と思ったわけで、それやったら自分が1番立ったらええじゃないかっていうね笑。
1番上司に
そうそう。だから、自分でいろいろ好きに運営できる立場になるのがその自分の能力を生かせるっていう風に思ったのはそのころからかな。新しい教室長とのうまくいかなかったりを経験してから思うようになったな。
それで今の校舎で始めようと思ったってことですね
そうやね。実際にそれが実現したのはちょうど30歳かな。ここ来たの30歳の時やから。
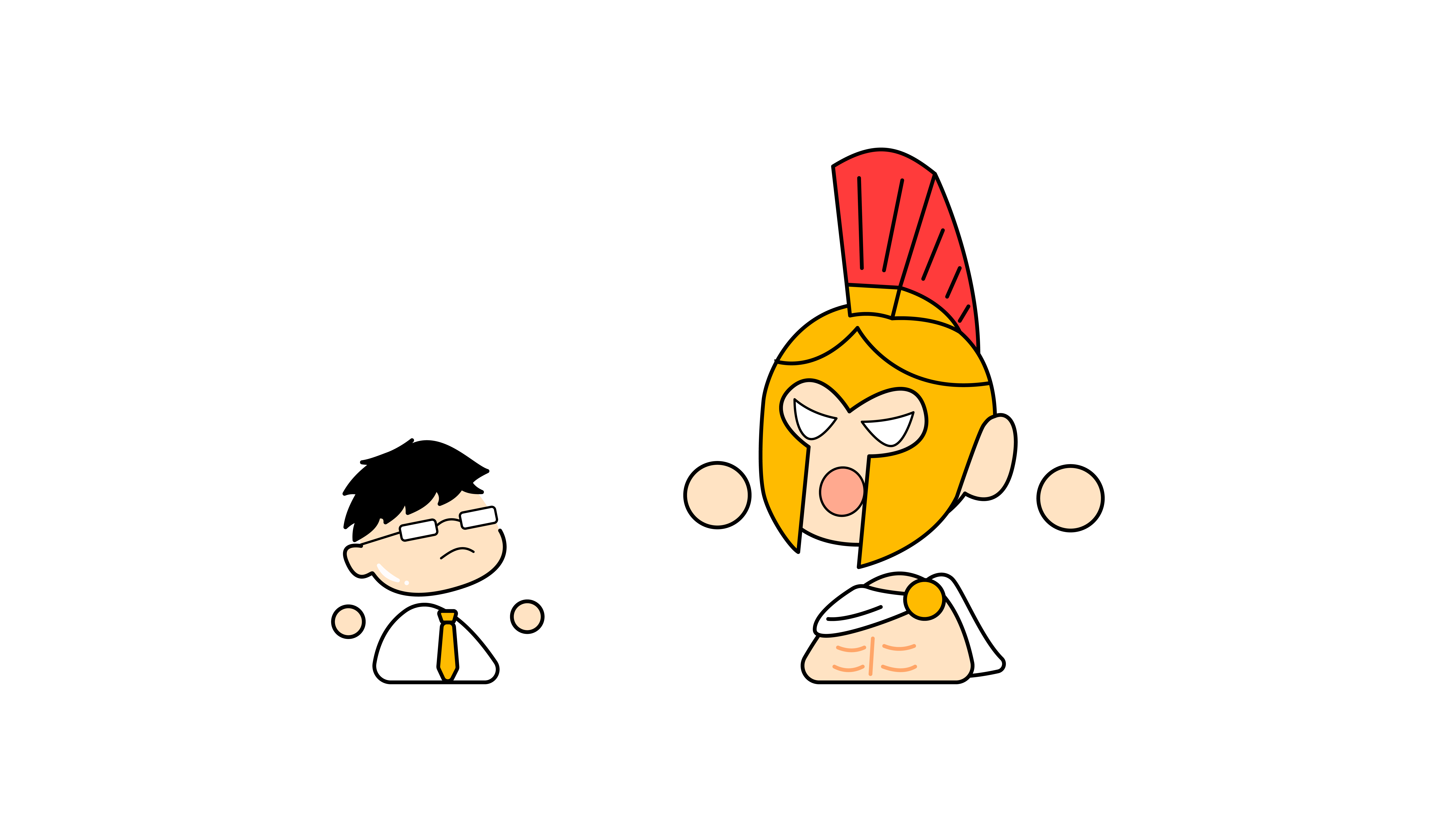
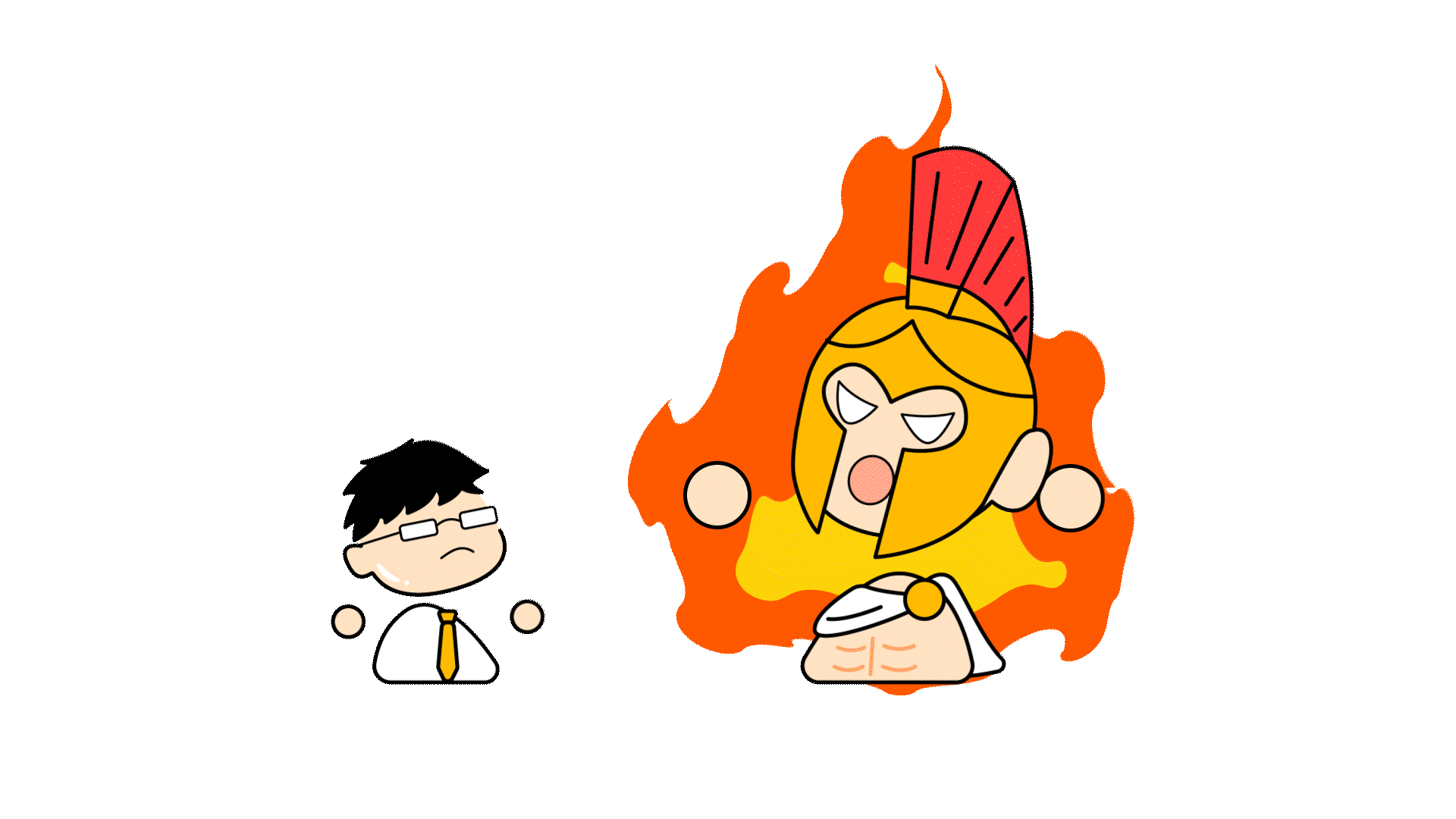
やっかいな上下関係。
上司の姿勢は部下の士気に大きく影響する。
正しいとは言えない上司の姿。
それが先生が独立を考えたきっかけなのだろう。
関西塾大阪校で始めたのは何かきっかけがあったんですか?
それはね、その、20代最初にアルバイトしてた頃に出会った先生がおんねんけど、その当時は同じ大学生やわ。で、その人が先に今の関西塾の別の教室で塾長をしてたわけよ。で、その人からたまたま電話がかかってきて、「1つ教室があるんやけど、やってみいひんか。」みたいな声がかかったんでね。よく話聞いてみると、自分で授業も組み立てれるし、その教室の塾長の裁量でいろんなことができるっていう形式やったんよね。もう、これはやるしかないなと。そういう縁もあって、たまたま念願かなってここにつけたわけやな。
その方とは、自分で教室を持って塾をやってみたいっていうのは話していたりはしたんですか?
そんなことはなくて、あん時聞いたのは、なんかこう、ふっと僕の顔が頭に思い浮かんだらしい笑。関西塾の理事長がこの地区に、今人口増えてるから、塾を開きたいから誰か人おらんか。って塾長会議っていうのが合ってそこの議題に上がったのね。その人の頭の中に僕が思い浮かんだらしい。で、そこで1人いますよって理事長に声をかけてくれて、すぐ僕んとこに連絡して。
そうなんですね
で、じゃあ一回話聞くわということで、その理事長と僕と、教えてくれた人3人で一緒に話をして、じゃあやらせていただきますっていうそんな感じ。
なんていうか、天の声みたいな感じやな笑
確かに笑
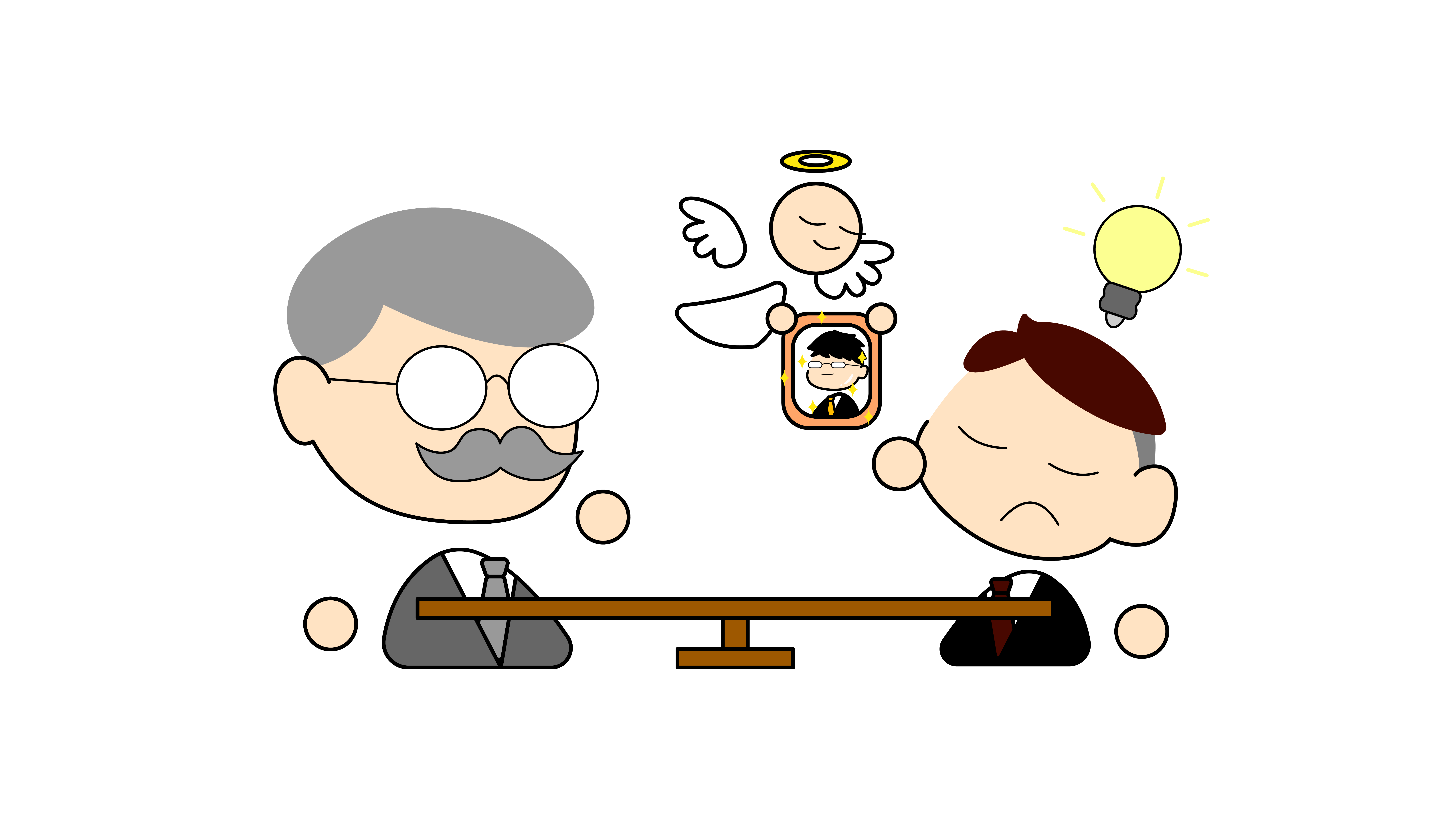
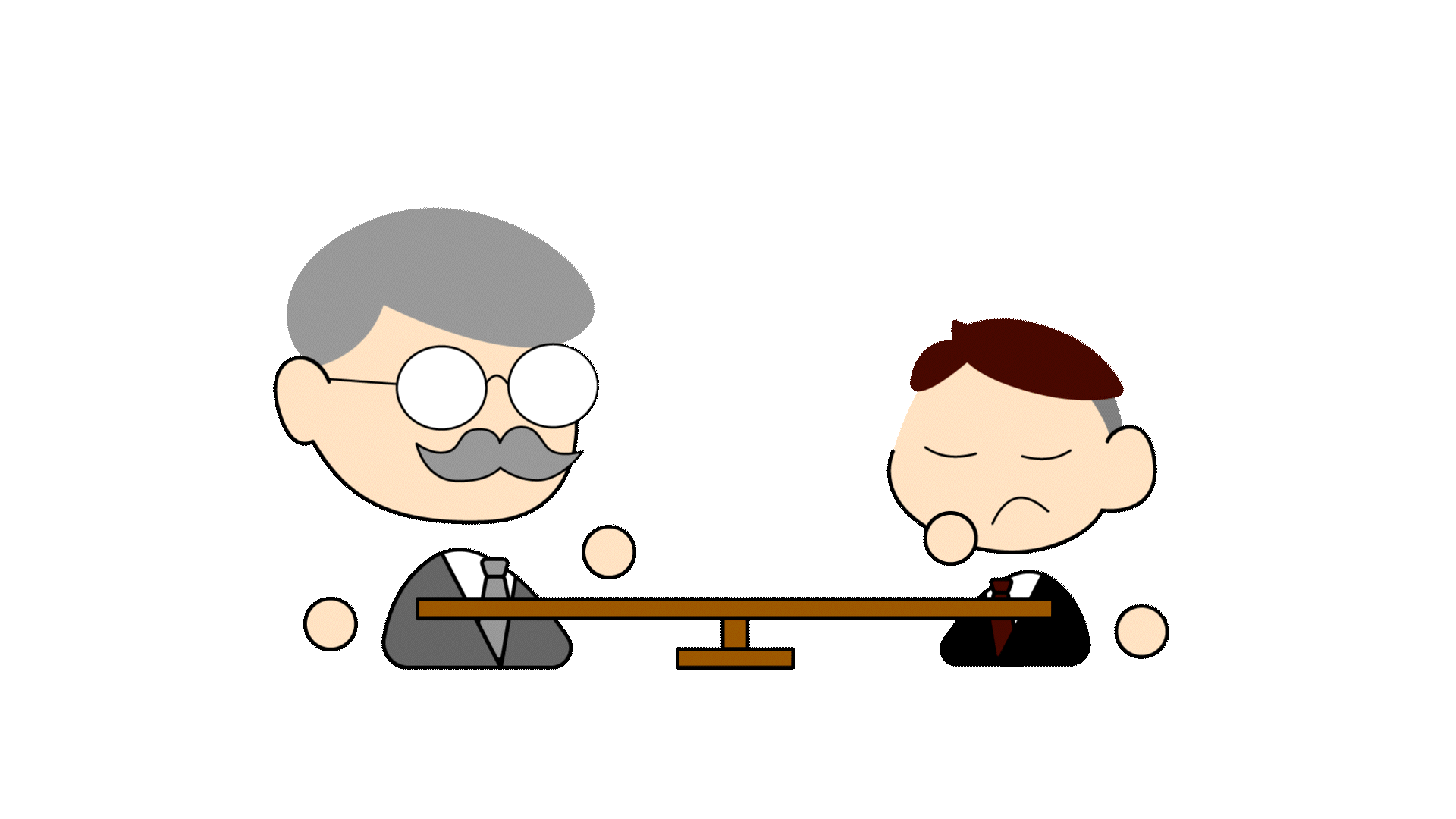
アルバイト時代の縁。
塾と真剣に向き合いつづけてきた先生。
先生の努力は誰もが知るところだったのだろう。
第3章:塾長の道
今年で(今の塾が始まって)何年目ですか?
10、15年目か。次で15年目かな。
始まった最初はどうでしたか、気持ちとか。
あれやね、なめてた笑。まあ、うまくいかないことの方がやっぱり多いね。イメージはしてたけど、イメージ通りいったことはほとんどなかったな。まず、(生徒が)集まらんかったね。すぐには。
僕が通ってた頃って、どんな感じでしたか?
あの時はもう軌道に乗ってたな笑。完全に、もう手応え掴んで、これでいけるわって。
タイミングってありましたか?先生的にもうこれは大丈夫やなみたいな
何をどうすれば結果が出るのかって、やっぱ最初わからんかったんよね。例えば、チラシを何枚巻いたらどんだけ反応があるとか、そういうのもわからへんし、いろいろやってみても、なんかやっぱりうまくいかない。だから、やっぱり試行錯誤。繰り返していくうちに、こうしたらこういう結果が返ってくるなって言うのが分かってきたのと。あとは自分なりにも勉強して、やっぱりその授業の必要なことって言うか市場調査やね。この地域にはどういう事業需要があるのかっていうことのマーケティング。それから誠実さっていうんかな、こう、自分にできることできないことを確実に相手には伝えていくっていう真面目さ、誠実さ。この2つ(マーケティングと誠実さ)があれば、何とかやっていけるんじゃないかっていう。手ごたえを掴んだのが5年目ぐらいかな。
大変ですね、本当に。
そうやね、その(5年の)間にもどんどん(生徒は)増えていってんねん。着々と増えてはいたんやけど、なんていうんかな、確信はなくて。増えてはいるけどなんでこういう結果になってるのかっていうのがやっぱり腑に落ちないっていう分があって心の中は怖いわけ。
確かに、いつ崩れるかも何も分からないわけですもんね
そうそう。根拠がないから、増えてるのはいいんやけど、なんでこの結果になってるのかっていうのが分からない。(生徒が)少ないなら少ないで、ちゃんとその原因っていうのが自分で分かってれば怖くないのよ。次ちゃんとこういう手を打って、また頑張っていこうみたいな、そういう風につながっていけるから。そう、うまくいってても行ってなくても不安やったと思うわ最初の3、4年目ぐらいは。
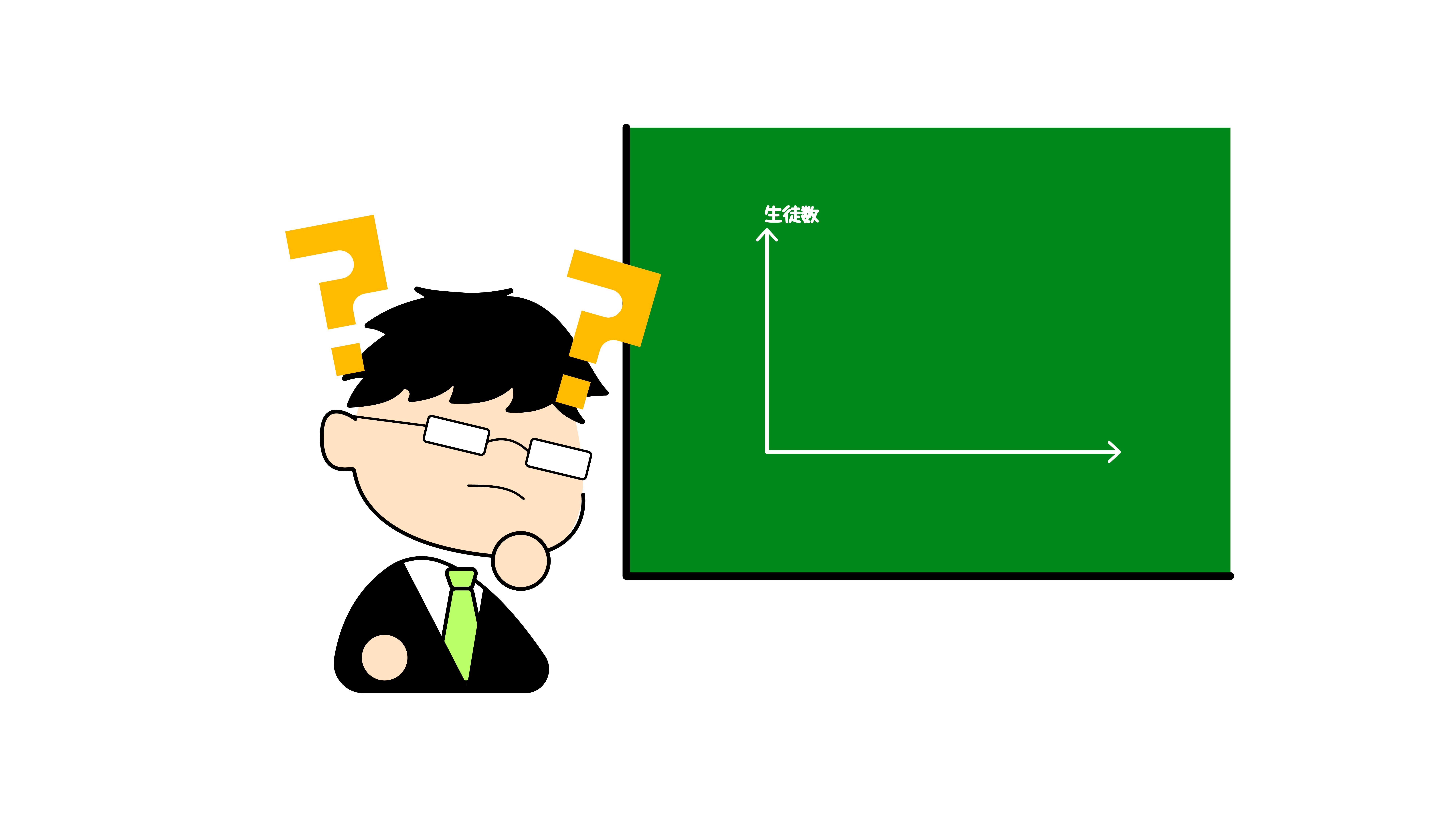
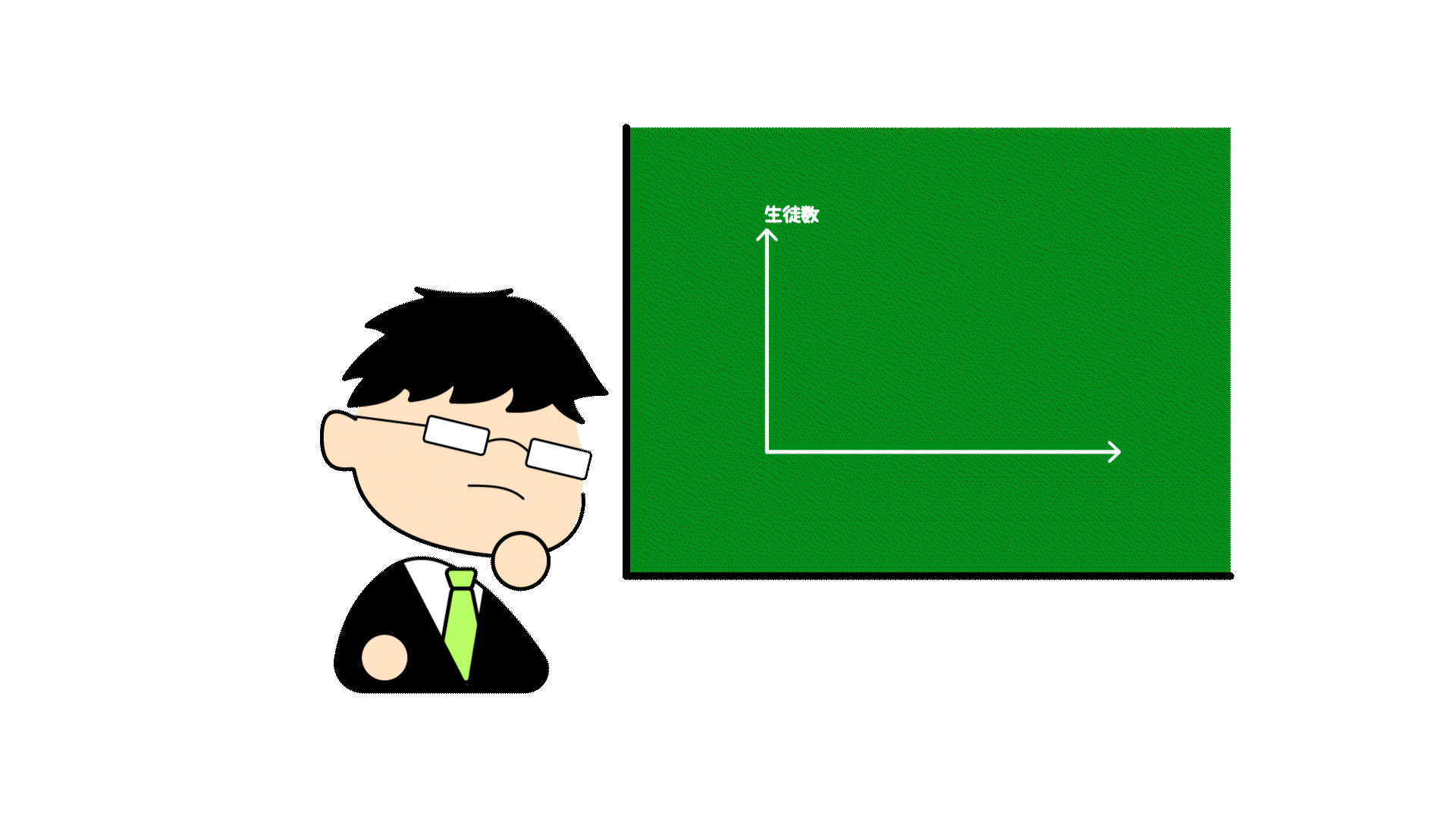
塾長としての第一歩を踏み出す。
初めは分からないことだらけだったそうだ。
集団と個別の間の授業方式をとった理由とかきっかけはありますか?
塾のスタイルっていっぱいあるよな。色々あるけど、その何がベストってのはまずないわ。集団には集団の良さがある、個別にも個別の良さがあるんだから、そういうどんな授業スタイルにも合う子ってやっぱいない。いないよね。
そうですね
その中で、なんで僕がこのシステムを選んだかって言ったら、最初僕が塾の先生をバイトとして始めたのが1対2の個別指導やったわけ。で、それはそれでもちろん全然いいんやけど、どうしてもなんか甘えが出る。こう近すぎるから先生と生徒の距離がね。だから、生徒自身が自分で考えてできることも、こう質問してきたり、なかなか自分で考えて物事を進めていく、そういう経験っていうのがなかなか養いづらい。で、個別の要素も取り入れ、集団の要素も取り入れた、中途半端って言われたらそれまでなんやけど、僕の中ではハイブリッドなんだよね。
いいとこ取りみたいな感じで。
そう。だから、本当に助けが必要な時はちゃんと助けるし、かといっていつでも助けるわけではなくて、自分で考えて、どうやったら問題解けるかなとか、どうやったら成績が上がるか、どのペースで勉強したらいいかっていう自分でそういう考えるきっかけっていうのが必要なんで。でこの中途半端なスタイルをやろうと笑
どのくらいからこのハイブリッドがいいなって考え始めたとかはありますか?
教務をやったって話したやん。で、教務やる中で、個別の教室があって、個別のいいやり方を教えたり、集団があって、その集団のやり方を教えたりする中で、そのハイブリッド式がいいんじゃないかっていうのはそこでたどり着いたね。
実際今の塾で初めて実践してみてうまくいったりいかなかったりは多かったですか?
まあまあ、なんていうんかな。まずこのシステムを理解してもらうのが難しかったね最初は。「どういう塾ですか」って言われて一言では言われへんからな。だから。それが受け入れられるかってどうかっていう心配と不安はあったけど、自信はあったんで。ただやっぱり、最初(人が)集まらんかったって言ったやろ。それがあったからやっぱり徐々に不安には変わっていったけどね。
個別塾と集団塾のハイブリッド式。
講師だけでなく教務も経験したからこその選択だったそうだ。
多くの視点から塾を見てきた集大成とも言えるのではないだろうか。
塾をやっていく上で1番意識していることはなんですか?心がけてることとか
でも、1番心がけてるのは生徒との信頼関係づくりやな。そのための努力は惜しまないって感じ。そこは強みかなって思うな。だから、雑談とかは、ようするな。ようしたやろ笑
いっぱいしました笑
いろんな話したよな。勉強だけのつながりってやっぱ無理よね。やっぱりこの人が言うんだったら間違いないかなっていう。やっぱり勉強ってなかなか好きでやる子って少ない。で、好きでやる子は塾には来んからね。塾に来てるってことはやっぱり自分から進んで勉強しない子が多いんで、それをやっぱり(勉強)させようと思ったらやっぱりめっちゃ勉強できるとか、教え方がうまいとか、それとはまた別のところがやっぱ必要や。逆に信頼関係さえあればもうなんもいらんのちゃうかなってね笑。
信頼があれば
そう。そのための努力をしてきたって感じかな。
忙しい中ありがとうございました
いえいえいえ!こちらこそありがとうね。いつでもおいでね!
次帰るとき、行きます!今日はありがとうございました!
生徒との信頼関係を築く。
これが生徒の勉強をサポートするうえでなくてはならない存在だという。
先生には勉強のことだけではなく、
多くのことで支えていただいたことを思い出した。